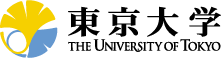共催シンポジウム「胎児期からの脳発達:発達保育実践政策学の追究」
- 日時
- 2021年2月8日 (月) 14:00〜16:00
- 場所
- オンライン開催(Zoomウェビナー)
- 共催
- 東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター(Cedep)
日本学術会議第一部心理学·教育学委員会 - 後援
- 日本学術会議
- お申し込み
- 先着450名 参加費無料
企画趣旨
近年、生涯にわたる健康や疾病、教育等の問題において「人生最初期の発達」の重要性が注目されています。本シンポジウムでは、医学・生物学分野で研究が進んでいる胎児期からの脳発達に焦点を当て、大脳皮質の発生・発達のプロセスや、早期環境が脳や認知機能の発達に与える影響について議論します。
プログラム
| 総合司会 | 野澤 祥子(東京大学大学院教育学研究科 准教授) |
|---|---|
| 企画趣旨説明 (14:00~) |
遠藤 利彦(日本学術会議第一部会員・東京大学大学院教育学研究科 教授) |
| 第1部:講演 (14:05~15:15) |
講演①:丸山 千秋(東京都医学総合研究所 脳神経回路形成プロジェクト プロジェクトリーダー) 「大脳新皮質形成の仕組み~神経発生学研究から~」 講演②:城所 博之(名古屋大学 医学部附属病院 小児科 助教) 「大脳新皮質形成の仕組み~ヒト早産児研究から~」 |
| 第2部:パネル ディスカッション (15:25~15:55) |
パネリスト: 松井 三枝 (日本学術会議第一部会員・金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 教授) 丸山 千秋 (東京都医学総合研究所 脳神経回路形成プロジェクト プロジェクトリーダー) 城所 博之 (名古屋大学 医学部附属病院 小児科 助教) 多賀 厳太郎(東京大学大学院教育学研究科 教授) |
| 閉会挨拶 (15:55~16:00) |
秋田 喜代美(東京大学大学院教育学研究科教授 研究科長) |
開催報告
「大脳新皮質形成の仕組み~神経発生学研究から~」
丸山 千秋 先生(東京都医学総合研究所 脳神経回路形成プロジェクト プロジェクトリーダー)
(要約 渡辺 はま:東京大学大学院教育学研究科特任准教授)
1. 哺乳類の脳の特徴とは?
哺乳類以外の生物と哺乳類では、脳の部品は似ているが、大脳新皮質(特に前頭葉)は哺乳類独特の脳領域である。健康な状態を保つためには、脳の様々な領域における神経細胞とグリアの活動が重要であり、また時として疾患につながることもある。特に、興奮性ニューロンと抑制性ニューロンの調和(E/Iバランス)の乱れを理解することが重要である。大脳皮質はより複雑な神経回路形成を実現してきたが、そういった脳の進化にはトレードオフもある。すなわち、精神疾患(脳形成異常、自閉症、うつ病、ADHD、アスペルガー症候群、統合失調症等)の発症リスクの増大が考えられる。
胎生期のマウスの大脳皮質培養ニューロンを観察することにより、胎児期から新生児期におけるヒトの脳発達に関する理解を深めることができる。神経線維を染色することによって、脳の神経回路ができていく様子を調べてみると、マウスでは4日間で脳の神経回路ができることが明らかになった。その際の細胞の配置が生命にとってとても重要なものとなる。特に大脳新皮質を観察してみると、6層構造になっていて、それぞれの層が脳のどの領域に投射されているかが決まっている。
ヒトに関して考えてみると、層構造の乱れが様々な疾患(滑脳症、統合失調症等)の原因になっているのではないかと考えられる。ニューロンが生まれて層構造ができるのは、胎児期の前半という大変早い時期に限られている。すなわち層構造への細胞の配置は、受胎後25週にはすでに完了してしまうのである。この時期にいったい何が起きているのだろうか。
2. マウスを用いて脳形成過程を理解する
胎児の脳は、ヒトとマウスでとても似ている。胎生期のマウスの脳神経細胞に、観察しやすいようにラベルをつけてスライスを作成し、それを培養することで、脳神経細胞が6層構造構築過程で、どのように移動していくか観察することができる。ニワトリの脳では、細胞がランダムに動くのに対して、マウスの脳では、細胞は決まった形に制御されて動くことがわかった。つまり、脳神経細胞の移動の様式が、鳥類と哺乳類では違っており、哺乳類では放射状に移動していることが明らかになってきた。これは多数のニューロンを効率よく移動させる仕組みになっていると思われる。
さらに最初の方の層では多極性細胞(ヒトデ型の細胞)だったものが、中間層であるサブプレートに到達すると、双極性細胞(シュッとした細長い形の細胞)になり、ロコモーションモード(移動するモード)になることがわかってきた。
3. サブプレートニューロンの自発活動と脳形成
ヒトの脳には、発生と同時に誕生し急速に成熟するが、生後間もない時期までにほとんどが死んでしまう(細胞死してしまう)、サブプレートニューロンと呼ばれるニューロンがある。サブプレートニューロンは、脳の視床という組織から皮質への投射をガイドする機能があることは知られていたが、「移動」に関わる機能は知られていなかった。そこで、マウスの脳を使って、移動がうまくいかないニューロン(障害のあるニューロン)を人工的に作ってみると、ある「境界」にぶつかると移動が止まってしまうことがわかった。その境界がサブプレート層である。
ニューロンがこのサブプレート層に到達すると、多極性から双極性に形を変える。そして、スピードアップして上層へと進んでいくのである。通常、12時間ほどサブプレート層に立ち止まった後、スッと上層に向かうのであるが、障害があるニューロンは、立ち止まったままになってしまうのである。ここで何が起こっているのか、何らかのシグナル(信号)のやりとりがあるのかを調べてみると、移動しているニューロンがサブプレート層を通過する際、細胞内のカルシウム濃度が一過的に上がることがわかった。サブプレート層は、下に向かって突起を出しており、移動ニューロンと直接コンタクトを取っていること、そこにはシナプス小胞があることを突き止めたのである。
またサブプレートニューロンは、胎生中期の時点で自発神経活動をしている。この自発活動が、ニューロンの上層への移動に何らかの役割を果たしているのかを調べるために、人工的にサブプレートニューロンの自発活動を抑制してみると、ニューロンの上層への移動ができなくなってしまった。したがって、サブプレートニューロンの自発神経活動は、移動モードへの変換に寄与していることが明らかになった。
ところで、多極性細胞の周りで局所的にグルタミン酸濃度を上げてみる、ということも試してみた。すると、移動スピードがどんどん早まって上層に向かう様子が観察された。よって、サブプレートニューロンの自発神経活動は、効率よくニューロンが配置されるための重要な仕組みであると言える。
4. ヒトの脳発達に対する考察
ヒト脳の発達過程には、経験(感覚刺激)に依存する要因(外的要因)と、神経活動に依存する要因(内的要因)があると考えられ、サブプレートニューロンは後者に当たる。ヒト胎児のサブプレートニューロンは、受胎後26-27週(脳にしわが出てくる頃)にもっとも厚くなる。また、受胎後20週の脳のスライス培養で、サブプレートニューロンの自発神経活動があることもわかってきた。重要なことは、サブプレートニューロンは、脳構築の基礎構築の時期に活動し、そして早々と消えていく、ということである。
ヒトの胎児・新生児には自発運動(General Movement)という、外界からの刺激に依存しない運動があることが知られており、たとえば将来自閉症となった児の新生児期の自発運動は、定型発達の児と異なる特徴があるという研究報告がある。こういった特徴に、サブプレートニューロンの発達・個人差が関係している可能性があるかもしれない。
また、サブプレートニューロンは、発達のごく初期に一過的な自発活動を起こし、脳の神経回路の構築をつかさどる。そして、生後すぐの時期に消失する(細胞死、アポトーシス)。最近、この消失がうまくいかないと、何らかの疾患につながるのではないかという仮説が生まれている。一方、サブプレートニューロンが、出生後も残っていて、重要な役割を果たしている可能性もある。例えば、サブプレートニューロンは、オレキシン作動性であることが報告されており、睡眠や意識の調節との関係なども指摘されている。
このように、ヒトの脳の「基礎工事」の時期である胎児期において、サブプレートニューロンは、大脳皮質の司令塔として機能しているのではないだろうか。
まとめ
- 哺乳類の大脳皮質は6層構造を持つ
- 未熟な神経細胞である移動ニューロンは、サブプレートニューロンからのシナプス伝達により細胞形態と移動モードの変換が促される
- リスト形式
- サブプレートニューロンの自発神経活動による脳構築は、生涯にわたって脳発達に影響を及ぼす
「大脳新皮質形成の仕組み~ヒト早産児研究から~」
城所 博之 先生(名古屋大学 医学部附属病院 小児科 助教)
(要約 渡辺 はま:東京大学大学院教育学研究科特任准教授)
1. (超)早産児と神経学的予後
早産児(在胎週数37週未満)、超早産児(在胎週数28週未満)あるいは低出生体重児(2,500g未満)、超低出生体重児(1,000g未満)の児の神経学的予後について考えてみる。在胎週数35週未満あるいは出生体重2,000g未満の児の多くはNICUへ入院する。生存した状態で退院する率(生存退院率)の変化を見ると、在胎週数23, 24週あたりでの率が年々高くなってきている。愛知県の事例では、58,669名を対象とした生存退院率は88%であるが、18か月、3歳、6歳の予後を見ると、脳性まひをはじめとした疾患があったり、なんらかのリハビリを要したり、あるいはIQが低い等のケースが一定数みられる。フランスやオーストラリアの事例を見ても、早産児において視聴覚障害、発達障害、神経学的障害、精神疾患が高確率で生じることが報告されており、彼らは、運動、感覚、認知、教育、心理のあらゆる面で問題を抱えていると考えられる。
生存率は向上しており、重度の脳障害も減少しているにもかかわらず、なぜ長期神経発達予後は向上しないのだろうか、という問題を考えていく。神経発達と関連する周産期の要因は、母体の要因と早産児の要因に分けられる。早産児のMRI画像を見ると、脳室周囲白質軟化症(Periventricular leukomalacia, PVL)、脳室内出血 (Intraventricular hemorrhage, IVH)、小脳出血(Cerebellar hemorrhage, CH)といったいわゆる古典的脳障害では説明できず、現在の診断基準では早産児の問題を評価できないケースがある。
早産児における新生児期は、脳がダイナミックな発達を示す時期にあたる。たとえば、受胎後22-36週では、脳のしわが2倍になる。早産児と正期産児に関して、いずれも修正40週の時点で脳の様子を比較すると、早産児において脳の表面積が小さく、しわも少ないことが報告されている。また早産児は脳全体でしわの溝(脳溝)が浅いわけではなく、特定の領域の脳溝が浅い(領域特異性がある)ことが明らかになっている。また、在胎週数と脳の灰白質体積が相関しており、こちらも領域特異性があることが報告されている。早産児の障害は多様性があり、白質に加えて、視床、脳幹、小脳の体積が少ないとの報告もある。早産児では修正40週での脳構造に変容が見られることが報告されており、それがその後の発達におけるさまざまな問題につながっていることも考えられる。
2. サブプレートニューロン
サブプレートニューロンは、受胎後22-34週をピークとして40週までに死滅する(アポトーシス)という特徴を持っており、皮質形成以前にシナプス形成の場を提供する、いわば「ガイド」の役割を担っていると考えられている。
マウスの神経活動を計測してみると、体動により体性感覚皮質にspindle burst(紡錘波群発)が観察される。またヒト早産児でも、末梢の触覚刺激によって体性感覚野のC3領域でdelta brushという波形が誘発される。さらには聴覚、視覚刺激によってもそれぞれ、聴覚野のT3、T4や視覚野のO1、O2でdelta brushが観察される。大脳皮質切片に電極を刺すことによっても、こういった紡錘波群発が起きるため、delta brushは大脳皮質に内在する活動であると考えられている。さらに、サブプレート層を切断すると紡錘波群発が起きなくなるため、紡錘波群発にはサブプレート層が不可欠であると考えられる。
早産児の脳波においては、在胎28週頃からdelta brushが観察される。deltaとは早産児特有の高振幅の徐波であり、brushとは持続時間が短い速波である。これらが複合して生起するので、delta brushと呼ばれる。delta brushは28週頃には脳の中心部に観察され、その後は後頭部に観察される。そして、40週で観察されなくなる。胎児期あるいは早産児において、このような自発性内在性電気活動が、神経系の発達に重要なのではないかと考えている。
早産児を診療していると、児の感覚入力が阻害されているかもしれないと考えることがある。筋弛緩薬や鎮痛剤の影響、ポジショニングやタッチケアといったディベロップメンタルケア、NICUにおける様々な環境などをどのようにするか、という問題と児への感覚入力の問題は切り離せない課題である。たとえば、聴覚システムの発達における母体の生理的音や声の役割、あるいはNICUにおける呼吸器やアラームの音などが発達にどのような影響を与えるのかに関しては、国内外で多くの研究が行われている。欧米では個室、日本では大部屋といったNICU環境の特徴があるが、その影響についても検討がなされている。ある研究例では、個室の環境では、2歳での言語発達指数が低く、aEEGでみた脳成熟度が低いこと、また上側頭溝に生理的に見られるはずの左右差が、個室で育った児には認めらない等、個室という環境が神経発達に負の影響を与えていることが報告されている(ただし、個室入院の児の保護者の来訪がたまたま少ない状況であった等、「個室」であること以外の要因がある可能性もあるので、解釈には注意を要する)。
早産児の脳波を調べると、聴覚刺激によって後側頭部にdelta brushが誘発される。特に、人工音では広い範囲でdelta brushが見られたが、人の声では中側頭部に限定された反応が見られた。また、delta brushは32週ごろにピークを迎えることが知られているが、超低出生体重児のbrushの出現頻度と予後の関係を調べてみると、後に発達が遅れた児は、発達の遅れが見られなかった児に比べて、週数が上がっても(成長しても)delta brushが出現していたことが明らかになった。このことから、本来は消失(アポトーシス)するはずのサブプレートニューロンが多く残存してしまい、異常なネットワークを作ってしまうのでは、という仮説が浮かび上がる。また、ヒトでは32-34週でdelta brushが多く観察されるが、それらと35週以降に見られるdelta brushは何らかの違いがあるのではないか、という疑問も生じる。
今後は、EEGとNIRSの同時計測等の手法も取り入れつつ、胎生期におけるサブプレートニューロンの変容が神経発達に及ぼす効果の解析をしていきたい。
最後に
出生数の減少、少子化が進む社会において、医学、保育、教育、スポーツなど、あらゆる分野でこどもの健全な脳の発達に対する理解が求められる。少子高齢化社会において、胎児の脳や早産児の脳の理解の重要性は増すばかりである。
パネルディスカッション
パネリスト:
2人の講演者の共通項である「サブプレートニューロン」を中心に、議論が展開された。
Q. delta brushはサブプレートニューロンと関係しているのか?(松井)
A. マウスで見ているものと全く同じかどうかはわからないが、ヒトの24週までとマウスの4日までの脳の発達はとてもよく似ていて、脳波も似ているため、ヒトとマウスのサブプレートもリンクしていると考えている。(城所)
Q. NICUのありかたとして個室化がいいのか?現状はどうなのか?(松井)
A. 欧米は個室化が進み、あらゆる雑音が少なくなるようになっている。個室化も悪い影響だけではないのでは、という知見も報告されている。(城所)
Q. 発達の問題を1歳半と3歳時点の認知機能で評価すると、1歳半では遅れていても、3歳でキャッチアップしている児も見られた。遅れたままの群とキャッチアップする群がいることについて、どんな考え方があるか?(松井)
A. キャッチアップする児がいる、という点に関して同じ実感を持っている。早産児は最初は遅れているけど、だんだんキャッチアップすることも知られている。キャッチアップする群とそうでない群の違いに、サブプレートが関係しているのか、それ以外の脳の構造が関係しているのかについては、多数例の検討を重ねる必要がある。(城所)
Q. 母体側の要因がサブプレートにどういう影響を及ぼすのか?(参加者、多賀)
A. 母体側の要因がサブプレートにどういった影響を与えるかについては、動物実験でもまだわかっていない。覚せい剤・ビタミンの過剰は妊婦によくないと言われているが、そのメカニズムはわかっていない。アルコールやタバコはニューロンの移動に影響を与えるとは言われている。どうすればサブプレートが活発になるのかはわかっておらず、今後の研究課題である。(丸山)
Q. 栄養を脳に送り届けるためには、血管とグリアとニューロンの相互作用が重要だが、その中でも発達期にサブプレートニューロンとグリアは、どのような関係にあるか?(参加者および多賀)
A. グリアがサブプレートにどういう影響を与えているかは、今後の検討課題である。(丸山)
Q. 胎児期にサブプレートが一過的に増え、そして消えるということと、環境において刺激を与えることがいいのか悪いのか、といったことの関係性は?(参加者、多賀)
A.サブプレートの活動を観察できるものとしてdelta brushを取り上げているが、ほかの形でもサブプレートを構造的・機能的に定量評価できると、サブプレートが予後にどう直結するのかわかるのではないかと考えている。刺激が多ければいいのか、どんな質があればいいのかは現時点では答えられない。(城所)
Q. 胎児におけるサブプレートの異常を発見することは可能か?(丸山)
A. 胎児期のサブプレートを研究するのは難しいが、脳磁図を用いて、胎児の脳から生じるdelta brushを読み取るという研究はある。いずれは、胎児においてdelta brushを計測できる技術が出てくることに期待。胎児MRIで構造的な評価はできる。(城所)
Q. 自発運動(General Movement)とサブプレートの関係は?(丸山)
A. GMの脳の機序はわからないが、サブプレートと自発運動は、どちらも「自発的」な活動であり、また、GMとサブプレートのdelta brushの頻度を見ると、いずれも37週あたりが重要という点が似ている。したがって、関係しているのではないか、という仮説を持っている。自発運動がサブプレート由来かもしれない、という仮説を立ててトライすることはできる。(多賀)
Q. 今後、どういった研究連携の可能性があるか?(丸山)
A. 動物実験をやっている研究者と、ヒトの構造・機能発達を研究している研究者が情報を交換しあってやっていくと、もっとわかってくることが多いだろう。分子的なサブプレートニューロンの研究と、ヒトの研究の双方から取り組むことによって、将来的にはサブプレートニューロンの機能分担までわかるとよい。(丸山)
まとめ
生涯を通した発達における個人差は重要な課題である。サブプレートニューロンと発達に関しては、直接の因果関係を調べにくいが、それでもトライしていくべき課題である。学術的には生物学の発生時期を扱う研究者から保育、福祉の現場の方々に至るまで広く関係する課題であり、さらには老年期の問題、精神疾患の問題にまで関係があるかもしれない。今後の研究の発展のポテンシャルを感じさせるシンポジウムであった。(多賀)