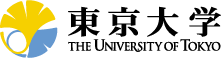- 日時
- 2015年10月21日 (水) 18:00〜20:00
- 場所
- 東京大学教育学部 第一会議室
- 講演
「強縦断データの多重スケール解析:複雑系の臨界点は予測可能か」
山本義春(東京大学大学院教育学研究科)
山本先生からは、①強縦断データの例と、②その分析・応用方法に関するご研究をわかりやすくご説明いただいた。
①Internet of Thing (IoT)と強縦断データIntensive Longitudinal Data(ILD)について 将来的に、身近にあるモノがインターネットを介して繋がることで、生体や健康に関連する様々なデータが、継時的・膨大に得られるようになる。生体情報や健康関連情報のデータをいかに取得するか、どのように分析するか、結果をいかに介入するか、健康リスクの評価や予防介入をいかにするかということが問題となる。こうしたデータが得られることは医療と公衆衛生の向上に結びつくが(リスクの初期検知やタイミングのよい介入・処方)、過剰な情報提供・情報管理が倫理的、経済的な問題を生じさせるという問題もある。 例1)米国NIHのMobile Health (m-Health):ライフログを収集・記録し医療や公衆衛生にビッグデータを活用していくためのモデル図が作成されている 例2)Ecological Momentary Assessment(EMA):携帯型コンピュータなどを電子日記として用いて、日常生活課での行動ログや自覚形状をリアルタイムに評価・記録を行う方法。心理評価に加え、生理情報も含むところがミソ。評価ができるなら、介入もできる(禁煙、体重減少、不安抑制等)。 例3)様々な強縦断データ:人間行動の連続モニタリングとモデリング Google Glass内蔵のemotionのセンサー(ユーザーの感情の読み取り)
②生体の「ゆらぎ」の研究 生体情報は複雑であり、実際に複雑動力学系にみられる多くの特徴を有する。そのような特徴を大量のデータからいかに抽出し、ダイナミクス(動態)の理解につなげるかということに関心を持ってきた。例えば、疾病が発症する、発達が新たな段階に入る、まさにその局面での動態の激変を、ゆらぎの性質を通じてみていきたいと考えている。 動態の激変によって疾病が発症・増悪するという概念は「dynamical disease」の名の下、一世を風靡したが、これは発達研究における「Dynamic Systems Approach」などもその影響を受けたものかと思う。Dynamical diseaseについては、最近情報通信技術の発展により変化の局面で大量にデータ(ゆらぎ)を得ることが可能になりつつあることから、発症予測やリスク評価の観点からも新たな展開が期待される。 Bio-behavioral ILDは大規模、多次元、多重スケール、複雑であり、5万、50万、500万回というデータの多さが特徴である。こうしたデータを非線形・非平衡動力学系の視点で解析すると、ちょっとしたパラメタの違いが劇的な変化につながること(分岐)、これまでの予想があたらないこと(確率的にも)、ミクロからマクロまでのゆらぎが混在すること(非周期・多重スケール性)、突然、想定外の大きなゆらぎ(間欠性)があることがわかる。Dynamical diseaseの制御パラメタの変化と病態遷移(分岐)を記述することで、こういう条件になると病状が発症すると予測できる。ただし、このモデルが唯一無二のモデルであると実証するのは(複雑なので)できないため実際の適応例はない。 非線形・非平衡動力学系の分野では、臨界相転移における臨界減衰“Critical Slowing Down”が様々なレベルで観測され、疾病だけでなく、株価や地震、気象などいろいろな事象において、初期警戒信号となる可能性が指摘されている。 研究例1)心不全を患った人の生存群と非生存群のdynamical disease制御パラメタの変化と病態遷移(分岐) 研究例2)健常者と大うつ病性患者の身体活動の活動モニタリング:休息時間の一週間分の確立分布を見る 研究例3)双極性障害の超長期連続計測:病態・病相変化の連続モニタリング:うつ様相のところと、軽躁病相(病相転移が起こるところを分析:臨床学的分岐点の検証) なお、本ご発表について詳細が知りたい場合には、山本先生のご講演(Gretsi 2015)をご覧いただきたい。http://www.gretsi.fr/colloque2015/video-conferences.html ※現在はアクセスできません
ディスカッションでは、発達や保育に対する、強縦断データの多重スケール解析の応用可能性(変化の兆候や瞬間の把握)について活発な議論が行われた。人間行動や発達の予測には、生体と外部環境の変化を両輪で捉える必要があるのではないかという指摘もあった。
報告:高橋翠(発達保育実践政策学センター特任助教)
「出生コホート研究の現状と課題」
山縣然太朗(山梨大学大学院医学工学総合研究部)
山縣先生からは、予防医学のお立場から、先生ご自身が関わってこられた出生コホート研究の経験をご紹介いただきつつ、出生コホート研究を行うことの意義や課題についてご講演いただいた。
予防医学においては、遺伝的要因をきちんと見ていく必要がある。決定的要因というよりも“かかりやすさ”を決める要因が大事である。従来の疫病研究は二点間比較の多変量解析が主であったが、出生コホート研究ではマルチレベル解析を行い、生涯を通じた因果関係モデルを明らかにすることを目的としている。トラジェクトリー(軌跡)の解析を行い、軌跡のどこに分岐点があるのか、そこで分岐する要因は何か、を見ていく。最終的には、政策基盤、研究基盤としての「ライフ・コース・リサーチ」の構築を目指している。
出生コホート研究の具体例として、例えば、妊娠届け出時から始まり、乳幼児健診、小学校入学時と、地域の基本的な保健情報を用いて軌跡を追う「甲州プロジェクト」、社会能力の発達パターンの解明と大規模コホート遂行技術の具体的知見の獲得を目的とした「すくすくコホート研究」、そして、環境省主導の全国規模の「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」についてご紹介いただいた。出生コホート研究を実施するにあたっては、検討すべき重要事項がある。例えば、子どもの発達を測定するための測定者の標準化、リサーチ・コーディネーターの育成、フォローアップ率維持のための手立て(例:家族の転居等に対応するための複数機関との連携)、多施設共同研究における研究ガバナンス等である。特に研究ガバナンスは重要であり、定期会合や手順書の作成等の工夫が必要である。
質疑応答では、出生コホート研究の関係教員だけでなく外部の研究者がエコチルに関わる具体的な方法や、論文執筆時のオーサーシップ、若手の育成、生体試料の保存、データセットの作成等、多岐にわたる活発な議論が続いた。最後は、コホート研究の結果をどのように協力者にお返しするかがもっとも難しい問題であり、この点については検討委員会の設置や基準の設定等行っているという話で締めくくられた。
報告:淀川裕美(発達保育実践政策学センター特任助教)
参加者の声
データの種類は異なるものの、山本先生、山縣先生ともに、大きなデータを集め、それを生かすという点で共通しており、非常に示唆に富んだ内容であった。複雑な生体信号を長期的に収集し、それを同時点で解析しながら介入を行う予測医療への応用可能性は、山本先生のお話の中でもあったように、今後、発達のダイナミクスに応用できる可能性を秘めているという点が非常に興味深いものであった。
山縣先生の出生コホート研究では、大きなデータを集める過程とその継続の苦難が語られると同時に、大規模コホート研究だからこそでき得る研究の魅力がつまったお話であった。日本の子ども達は日本独自の環境内で育つものであり、海外のコホートではなく、日本の調査内容を政策に生かすことは、保育政策の分野においても非常に重要な課題であることを改めて感じた。
研究を進めるにあたってぶつかる壁を、多分野の研究者の関わりによって崩し、道を切り開いていく力がこのセンターで毎月行われるセミナーにはあるように思い、今後の展開に大いに期待しつつ、自らも貢献できるよう努力したい。
報告:清水悦子(東京大学大学院教育学研究科身体教育学コース博士課程3年)