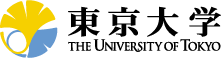- 日時
- 2018年4月25日 (水) 17:30〜19:00
- 場所
- 東京大学教育学部 第一会議室
- 講演
「早く産まれたまれた赤ちゃんの”泣き声”は何を伝えるか?―音響的、生理学的解析および心理学的指標からの検討―」
新屋 裕太(発達保育実践政策学センター)
早産児とは在胎週数37週で出生する子どもである。日本では医療の進歩により新生児の救命率が上昇しており、早産児(低出生体重児)の出生率は増加の一途をたどっている(10人に一人は低出生体重児)。低出生体重児は出生直後、新生児集中治療室(NICU)で過ごすことになる。この環境は子宮内と異なる光環境であり、過度な音環境(騒音)にさらされる。養育者との分離の経験に加え、出生の状況や経過によっては度重なる侵襲的な医療処置を経験することになる。
近年、早期の環境経験のネガティブな影響を指摘する報告が相次いでいる。早産児は発達障害と診断されるリスクが満期産児に比べて高く、例えば自閉症の罹患率は、在胎週数が短いほど高くなる傾向にある(在胎週数23~27週の児では満期産児に比べて3.2倍のリスクとなる;D' Onofrio et al., 2013 JAMA)。また、大規模なコホート研究から、重篤な疾患のない早産児でも、認知・言語発達の問題を抱えるリスクが高く、そのリスクは在胎週数が短いほど顕著であることが明らかにされている。早産児におけるこうした非定型発達は、すでに乳幼児期から指摘されており、発達早期から早産児の行動や神経生理面の発達を評価・支援していく必要がある。
乳児の「泣き声」は神経の成熟やストレスを測る「簡便な」指標であり、極めて高い声は、生後早期の神経疾患と関連することが指摘されている。早産児についても、満期産児に比べると、生後早期の泣き声が高いことが報告されているが、その際を生じさせるメカニズムや、在胎期間や身体サイズ、子宮内発育の程度といった要因とどのように関連するかは不明なままである。そこで新屋先生たちの研究グループは、予定日前後まで成長した早産児と満期産新生児を対象に、授乳前の泣き声を録音し、その音響的特徴とその関連要因(生理的要因、発達心理的要因)についての分析を行った。
一連の研究の結果から、早期に生まれた早産児ほど自発的な泣き声のピッチが高く、こうしたピッチの高さは、副交感神経活動の低下による喉頭部の緊張と部分的に関連することが明らかになった。ただし、早産児のピッチの高さと乳児期の認知発達との関連は見られなかったことから、必ずしも発達のリスクを反映するわけではなく、生後の経験による発達なども関与している可能性がある。特に、ピッチの高い泣きは親に緊張性を伝え、敏感な養育行動を促進しやすいことから、早期の環境への「適応」を反映している可能性も考えられる。また、比較的リスクの低い健康な早産児では、泣き声のメロディーのバリエーションが大きく、乳児期の言語や認知発達も良好だった。その理由として、生後早期から泣き声のメロディーの発達が進みやすい児では、複雑な音声制御に関わる皮質の発達が早い可能性が考えられる。さらに、こうした児では、大人との音声を介したコミュニケーションでの音声模倣などが促進されやすく、乳児期の言語獲得において優位性があった可能性がある。
今後の課題として、周産期以降の泣き声の発達やその神経生理的メカニズム、養育者側の知覚についても詳細な検討を行う必要がある。また、臨床応用としては、機械学習を応用した泣き声の特徴による発達評価法の開発や、親子間の音声コミュニケーションへの介入支援なども期待される。
「学校自己評価が教師間の協働に果たす効果に関する実証的研究―目標設定の主体に着目して―」
佐々木 織恵(発達保育実践政策学センター)
日本においては、2007年の学校教育法施行規則の改正により、学校自己評価の実施・公表が義務化されている。その制度は、学校の自主性・自律性拡大に伴い、校長を頂点とする組織的・一体的な教職員体制を確立する学校経営を重視するものであり、国による成果管理を特徴とするイギリスの学校評価制度や、統一的な質指標に基づいた成果管理を提起する OECDの学校評価研究とは明確に異なる。
本研究では学校評価におけるPDCAサイクルのうち、Plan(目標設定)の主体に着目した。目標設定の主体を校長とするか教員とするかは60-70年代の単層・重層構造論争に遡り、政策的にその主体を校長とすることで決着が着いた現代においても、研究者の間ではその是非について意見が分かれたままである。また、本研究では学校自己評価の効果として、学校教育がもたらした価値と効果についての教職員間の協働的な省察に着目しているが、この点に着目した実証的研究は限られている。
筆者は定量的、定性的手法を用いて、学校自己評価が協働に果たす影響、条件に関して実証的な研究を行った。定量的な研究からは、目標設定への教職員参加はおよそ7割の学校でなされていることが明らかになったが、学校自己評価の目標設定の段階への教職員参加が教職員間の協働にもたらす影響に、小中で違いが見られた。また定性的研究からは、教職員を含めた目標設定の取り組みの実施に果たす校長のリーダーシップや、自己評価における協議におけるミドルリーダーのリーダーシップが、自己評価を協働につなげる条件として示された。
保育・幼児教育段階で、教職員間の協働を向上させるような自己評価の在り方を考えるにあたっては、学校段階の特性を踏まえて、誰がどのように課題意識の統一を測る中で目標を設定するべきなのかについて考えていく必要があるだろう。