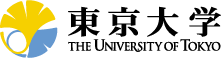- 日時
- 2016年5月11日 (水) 18:00〜20:00
- 場所
- 東京大学教育学部 第一会議室
- 講演
「幼児期の体力科学:逞しい心と体を育む保育プログラム」
春日晃章(岐阜大学教育学部/岐阜大学保育園/学校法人春日学園 はなぞの幼稚園・はなぞの北幼稚園)
春日先生には研究者・経営者(理事長)・保育現場統括者(園長)という三つの立場から子どもの体力についてお話しいただいた。ご報告ではまず子どもの体力の実態と近年の政策動向をご紹介下さった。ここ数年、子どもの体力に回復の兆しが見られると報道されているが、実際には小学校低学年の運動能力は改善しておらず、幼少期の体力向上が保育に求められているという。子どもが継続して多くの友達と群れながら運動遊びをすることは、丈夫な身体作りだけでなく強く優しい心や社会適応能力の発達にも役立つ。国の側では、幼児が様々な遊びを中心に毎日合計60分以上楽しく体を動かす必要があると明記した文部科学省の幼児期運動指針(平成23年)を策定し、幼児期における体力向上プログラムを強化している。
研究者の立場からは、独自に実施した幼児の体力テストのデータを基に多くの知見をご紹介いただいた。その一部を紹介すると、第一に子どもの体力テストの結果が想像以上に悪いと感じた保護者は、親子で外遊びをする頻度を増やす傾向がある。第二に、運動能力の個人差は走る・跳ぶ・投げるといった種目によって異なる。例えば、3歳から6歳にかけて走る力は等しく向上するが、投げる力では個人差が開いていく。第三に、運動能力の高い男児は誰とでも仲良くし何事にも粘り強く取り組むことができる。第四に、未就園2歳児の運動強度はプリスクールの保育中に高いので、集団で遊ぶことの重要性が示唆される。第五に、痩身児と過度な肥満児(肥満度20%以上)は標準と比べて運動能力が低い。興味深いことに、肥満度15%~20%の肥満児は筋肉量が多いからか標準以上の運動能力を持っている。第六に、運動能力は生育環境と関係しており、年上と年下の兄弟を持つ子どもはそれ以外の子どもと比べて運動能力が高い。小さい頃は年上の兄弟と遊び、ある程度大きくなったら年下の兄弟と遊べるからである。第七に、運動部への所属や運動指導は子どもの体力の向上に役立つ。年長のときに体力得点が低かった女児でも、小学6年時に運動部に所属していれば体力得点の上昇が見られる。また、春日先生は自ら指導プログラムハンドブックを作成し、子どもに対する運動指導を促進している。年中児に遠投を2ヶ月指導した結果、投球フォームと遠投距離が大きく改善されたという。
さらに、春日先生は経営者としても幼児の体力向上に取り組まれている。通常は年1回の運動会を年2回に増やし冬にも子どもが運動するきっかけを作った。運動会ではアルティメット玉入れといった独創的なプログラムを考案し、園の総合遊具も独自に開発している。子どもたちが楽しみながら体を動かす姿を写真と動画でご紹介下さった。最後に、保育現場統括者の立場から受け入れ園児数の拡大や認可保育所への移行といった課題を挙げていただいた。
報告:関智弘(発達保育実践政策学センター特任助教)
参加者の声
- 普段、成人女性の運動不足、体力不足の問題を強く認識しているので、幼児期からの体力増進はとても重要だと思う。春日先生の園のようなとりくみが、多くの保育現場でなされると良いと感じる。
日下桃子(医学系研究科健康科学・看護学専攻 博士課程) - 現在、公園でボール遊びができないなど、日常での運動が制限される一方で、クラブ活動など早期のスポーツ活動の専門化もすすんでいる印象を受けました。先生方の園のとりくみは大変すばらしいと感じましたが、そのような環境で小学校にすすむと、「スポーツを楽しむ」経験をした子とそうでない子の二極化は大きくなるのかなと思いました。
「食環境因子と脳機能」
川村 美笑子(金沢学院大学人間健康学部)
川村先生はもともと栄養生理学の基礎研究をされ、その基礎的知見と社会的実践との橋渡しに注力してこられた。本日のセミナーでは、そうした経験をふまえ、栄養学の変遷、食の意義、食物の摂取および消化・吸収のメカニズム、そして食環境と脳機能の関係についてお話いただいた。
栄養学は、食物栄養学から人間栄養学へと変遷してきた。物質代謝やエネルギー代謝の解明だけでなく‘何をどれだけ(どのように)食べるべきか’といった栄養学の実践もふまえ、学術面ではNutritional Scienceとしての人間栄養学、実践活動面ではDietaticsとしての応用栄養学として展開してきた。そもそも食べるという行為は、種の保存においてもっとも自然な営みである。その中で完全栄養食品は存在しないため、適正な食品選択と組み合わせが重要であるが、知識なしに意のままに食品を選択していては健康を損ねること(栄養障害・発達障害・知的障害)にも繋がっていく。そうした理解を深める必要から、食物の摂取や消化・吸収のメカニズム、食環境と脳機能についてご研究されてきた。
食物の摂取や消化・吸収については、栄養素の摂取だけでなく、体内での消化・吸収までを考える必要がある。つまり、食物の摂取行為だけでなく、代謝してエネルギーとして取り込み、あるいは体成分とする、というプロセス自体が重要である。例えば、摂食と生体リズムに関連があること、経口摂取により副交感神経の働きが強まり、自然治癒力や免疫力の活性化が促されることなどが分かっている。そうしたメカニズムをふまえて食物摂取、消化・吸収について考える必要がある。
さらに、食環境と脳機能についてお話いただいた。脳は活動のためにエネルギーが必要であり、脳の構成成分も脳内で合成される神経伝達物質など生理活性物質の素材も、食物に依存する。近年では脳組織や機能システムに可塑性があることが明らかになっており、脳機能と栄養についての研究が盛んに行われるようになっている。脳への栄養物質の取り込みは、血液脳関門を通じて行われ、神経伝達物質を介してさまざまな脳機能へと結びつく。脳への食成分透過性の異常(栄養物質が血液脳関門を超える際の異常)が発生した場合にうつや精神疾患、糖尿病等の心身症状が発症する。脳機能とそれによる心身の諸症状について考える際、食環境についてもおさえる必要がある(詳細はPPT資料をご参照いただきたい)。最後に、新しい栄養学の流れとして、(1)遺伝子栄養学(多型対応最適栄養、個人差の重視)、(2)時間栄養学(時間接収時刻、速度、順、配分)、(3)精神栄養学(最適精神活動活性化、精神障害の予防)、(4)一次予防栄養学(健康寿命、テロメア維持への寄与)が紹介され、いずれも食事摂取基準で作成されていない新項目であり、今後検討を要するとのことであった。
おわりに、脳を中心として食事、栄養、人のからだの三者がつながっている図とともに、情緒の安定、発育(心と身体)、生活習慣(食習慣)と学力、媒体、五感がつながっていますか?という問いかけがなされ、ご講演が締めくくられた。
報告:淀川裕美(発達保育実践政策学センター特任講師)
参加者の声
単に栄養素を摂取すればよいということではなく、何をいつどのように食べるかということが消化・吸収のメカニズムや脳機能と関わっていることを教えていただきました。近年、保育現場で「食育」への関心が高まっていますが、栄養学の面からも科学的エビデンスを提供していただくことで、食の大切さへの理解が深まると感じました。貴重なお話をどうもありがとうございました。