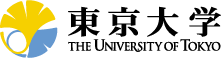- 日時
- 2017年1月25日 (水) 18:00〜20:00
- 場所
- 東京大学教育学部 赤門総合研究棟A210
- 講演
「発達性読み書き障害のすべて~就学後、早期に困らないために何ができるか~」
小枝 達也(国立成育医療研究センターこころの診療部)
小枝達也先生には、発達性読み書き障害(ディスレクシア)の診断と治療が可能になっていることをお話いただいた。ディスレクシアの子どもは、音韻処理に困難があり、単語を構成している音(オン)に分ける能力に欠けている。例えば「ねこ」は「ね」と「こ」という2つの音から構成されているということを認識する能力に困難がある。そのため、文章を読もうとすると、文字を1つ1つ拾って読むなどして極端に時間がかかり、その疲れから読み間違えも多くなる。文字を読むのが疲れるから本が嫌いになり、ますます本を読まなくなることで語彙や知識が身につかず学業不振に陥ってしまう。
小枝先生の研究によると、0.8%~2.1%の子どもたちがディスレクシアを抱えているが、そうした子どもを見つけるのは容易ではない。というのも、子どもは音読が苦手なことをうまくカモフラージュするからである。教科書を丸暗記したり、黙り込んだり、保健室に行ったり、騒いで授業妨害したりする。ディスレクシアの子どもたちは、音読が苦手なことを恥ずかしく思いながら、どうしていいか分からず困惑しているのである。こうした問題を少しでも解消するために、小枝先生はディスレクシアの診断方法と治療法の開発に取り組んできた。
診断方法としては特異的発達障害実践ガイドラインの作成に携わり、簡単な症状のチェック表と音読検査でディスレクシアを診断できるようになった。音読がどの程度速く正確であるのかに注目する点が特徴である。治療法ではT式ひらがな音読支援を開発し、2段階方式による音読指導とRTI(Response to Instruction)モデルによる早期発見を提案している。音読指導は、文字とその読みの対応を練習する解読指導から始め、音のまとまりを見分ける語彙指導に進む。そのうち解読指導の部分は独自開発の音読指導アプリによって自動化し、家庭や教室で簡単に音読指導をできるようにした。RTIモデルでは、小学校1年生の段階で、読み書きの苦手な子どもに音読指導を行いながら、その効果を繰り返し検証することでディスレクシアを早期に発見しようとしている。なお、T式ひらがな音読支援の詳細については、国立成育医療研究センターのHPを参照して下さい。
参加者の声
自分の小学校の同級生にも読み書きの苦手な子はいたが、当時は勉強嫌いで片付けられていた気がする。現在ではディスレクシアの診断方法と治療法があるので、学校の先生に正確な知識と意欲があれば多くの子どもたちが救われるだろう。ただし、先生は事務仕事などで多くの業務を抱えており、音読指導に手が回らない可能性がある。そこで、低学年の音読指導を担当する支援員を加配するといった行政支援が期待される。
報告:関智弘(発達保育実践政策学センター特任助教)
「赤ちゃんのあたたかな心を育む発達支援」
大城 昌平 (聖隷クリストファー大学大学院リハビリテーション科学研究科)
理学療法士として、低出生体重児の発達支援、評価、発達フォローに長年携わってこられた大城先生から、「ディベロップメンタルケア」の理論的背景と我が国における取り組みの実際、そしてその中で特に重要な考え方について、ご講演いただいた。
ご講演の前半では、まず我が国の現状が紹介された。出生児総数の約10%が2,500g未満で生まれる低出生体重児で、近年の医療技術の進歩により、500gほどで生まれる児でも3人に1人は生存する時代となった。また、小さく生まれるほど色々な発達障害をもつリスクが高く、低出生体重児の7~8割は発達障害をもつことも明らかにされている。「ディベロップメンタルケア」とは、そのような状況で、妊娠期から始まり出産時、入院中、そして乳児期、幼児期へと継続して、児やその家族への支援を包括的に行うための枠組みをさす。そこでは、ケアの環境や過程もアプローチ対象となっている。
我が国では、1958年頃に未熟児の治療が始まった。1970年代初期にNICUが開設され、1980年代には多くの命が助かるようになった。1990年代には、医療の改善により救命率がさらに上がり、後遺症無き生存が重視されるようになった。さらに2000年代に入ると、児だけでなく家族も含めた支援、また、児の脳とこころの両方を守ることが新生児医療の目的とされるようになり、その中でカンガルーケアなどの考えも広まっていった。
ディベロップメンタルケアの理論的背景には、3本の柱がある。①神経系(脳)の発達、②赤ちゃんの行動と発達、③赤ちゃんのこころの発達である。①神経系(脳)の発達とは、赤ちゃんの脳を守ることである。脳の発達過程のもっとも大事な時期を「感受期」(25~40週)と呼ぶが、この時期に生まれる児は、色々な外界の刺激を受けることになる。そのような児の脳をいかに守り育むかが課題である。②赤ちゃんの行動と発達という柱では、赤ちゃんは生得的な社会的相互作用の力をもって生まれた存在であり、その能力をうまく引き出すことによって、赤ちゃんの発達も促され、また、他者との関係も促されるのではないかと考えられる。最後に、③赤ちゃんのこころの発達とは、赤ちゃんの行動を通して赤ちゃんの心を理解しようとする考えである。新生児のこころを考えるにあたっては、養育者が赤ちゃんの行動から間主観的(intersubjectivity)に赤ちゃんのこころの状況を理解(把握)し、それを児に写し返すこと(鏡映化mirroring)によって、赤ちゃんと養育者の情緒的交流が生まれる。
以上の理論的背景をふまえ、ディベロップメンタルケアで特に大事にしているのは、低出生体重児がNICUで、なるべく母親のおなかの中に近い物理的・情緒的な環境を実現することである。また同時に、後述するように、親子の関係性を重視し、親の心の回復と子育てに対する親としての自信と誇りを育てる場としてもNICUを捉える必要がある。
ご講演の後半では、低出生体重児のディベロップメンタルケアの実際と、今後のディベロップメンタルケアへのご提言内容をお話くださった。ディベロップメンタルケアの概念的枠組みとしては、次の5つが挙げられる。①発達の3つの推進力(脳・環境・行動)、②家族中心のケア、③赤ちゃん-家族-スタッフの協働、④個別性(行動観察にもとづくケアの実践)、⑤強み(自己調整行動)を引き出すケア、である。①については、赤ちゃんの発達の推進力として、新生児行動(自律神経系、運動系、状態系、注意/相互作用系)の発達と、神経系の発達、環境要因の3つが相互に関連している。赤ちゃんを見る時には、この3つの要因で見ることが重要である。⑤の自己調整行動では、赤ちゃんへのストレスを緩和するとともに、赤ちゃんには自分で自分を落ち着かせる行動(自己調整行動)があり、それを支援するケアや関わりも求められる。例えば、赤ちゃんのストレスを緩和する方法として、赤ちゃんを包み込んであげる、赤ちゃんの行動を観察しながらゆっくり優しくケアするといった工夫がなされるようになってきている。低出生体重児にとって、自分で自分をコントロールできるようになることは、発達上きわめて重要な要素であると考えられる。また、②家族中心のケアに関しては、親子の触れ合いを大切にする1つの方法としてカンガルーケアが実施されている。できるだけ早い時期から母親が児を抱っこし、児がおっぱいを求めれば吸わせてあげる、といった生理的・情緒的なかかわりである。母子の愛着形成を支え、父親がそれをサポートする関係を支援することで、家族の絆が育まれる。また、③赤ちゃん-家族-スタッフの協働では、これまでNICUにおける児のケアを看護師等医療者が中心となって行われてきた。今では、両親の心情をみて、できるだけ早い時期から両親が赤ちゃんのケアに積極的に参加し、赤ちゃんとのかかわりや育児の練習をしていく支援を行う。その中で、親としての自信が育まれていくという。
以上のまとめとして、大城先生は次のことを提言していきたいと仰っていた。まず、やさしさ、穏やかさ、あたたかさといった情緒的環境を整えること。赤ちゃんの行動を視点として、自己調整を支援するケアを行うこと。両親や家族との協働と段階的なケア参加への移行し、家族の関係性を育てること。NICUが命を助ける場としてだけでなく、家族の物語を育む場としての機能を果たしていくこと。最後に、NICUの医学的な治療とディベロップメンタルケアとは、赤ちゃんが一人の人間として育つための車の両輪のようなものであると、力強く語られ、ご講演を締めくくられた。
参加者の声
本日の大城先生のご講演内容は、NICUでケアされ育っていく低出生体重児の「人間としての尊厳」にかかわるお話で、保育でも近年重視されている「子どもの最善の利益」の根源に繋がるものだと感じました。また、新生児医療の分野でも、家族やその他の環境要因も含めた関係論的アプローチが取られていることに期待を抱くと同時に、それが園生活・学校生活へといくつもの移行場面を乗り越えて継続していくこと、そのために多機関が連携することの重要性を痛感しました。研究の分野でも、領域の別を超えて連携して取り組み、新たな展望が開けることを願っています。本日は胸に迫るお話を、ありがとうございました。
報告:淀川裕美(発達保育実践政策学センター特任講師)